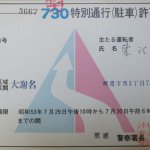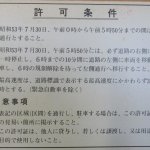ナナサンマルとは1978(昭和53)年7月30日のことで、沖縄県の道路通行方式が右側通行から左側通行に変更された日付に由来する。1972(昭和47)年5月15日に米国から沖縄が返還されて6年目の出来事だった。
沖縄返還後、ナナサンマルは「本土一体化」の一つの大きな象徴として捉えられる出来事であった。しかし、道路通行方式の変更は交差点や信号の構造、マイル表記からキロ表記の変更のみならず、道路を通行するバスやバス停など多岐にわたる対策が必要であった。
県民の足として活躍を続けるバスの大改革の日としてもナナサンマルは多くの人の記憶に残るものとなった。
今年は沖縄復帰50年の節目の年となるが、本日7月30日「ナナサンマル」にあたって44年前に何が行われたのか、2台だけ残る生き証人のバス車両の紹介を含めて改めて振り返ってみたい。
文/写真:石鎚 翼(特記をのぞく)
【画像ギャラリー】右側通行から左側通行への変更、沖縄ではこんな大事業が実際に行われた!!(11枚)画像ギャラリークルマは右側通行で速度表示もマイルだった
今年度上期のNHK連続テレビ小説「ちむどんどん」は沖縄が舞台である。山原地方に住む主人公たちが町へ出かける際に利用するバスが左ハンドル車であることに気づいた方も多いと思う。太平洋戦争によって米国に占領された沖縄は、米軍の軍令によって米国と同様、車両の右側通行が指示されていた。
その後1947(昭和22)年には、沖縄民政府(米国統治下における行政機関)による政令によって、右側通行が法制化され、1978年までの間、この状態が続いた。もちろん米国統治下では通行方式のみならず道路標識のデザイン、速度指示の単位(kmではなくマイル表示)も米国に倣ったものとされた(マイル表示は通行方式変更に先立ち、1968(昭和43)年にメートル法を適用)。
1972年に米国から沖縄が返還されると、日本政府は「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」を策定、地方自治の体制や通貨、教育など多岐にわたる制度を本土同様にすべく作業に着手した。この法の中で、道路交通については右側通行を存置しつつ、日本の道路交通法を適用し、必要な準備期間(3年以上)を経過したのち、政令によって左側通行に変更する、とされた。
これがナナサンマルの法的根拠である。これをもとに、1977(昭和52)年9月に「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第五十八条第一項の政令で定める日を定める政令」が公布され、ここで1978年7月30日に道路通行方式を変更することが定められた。