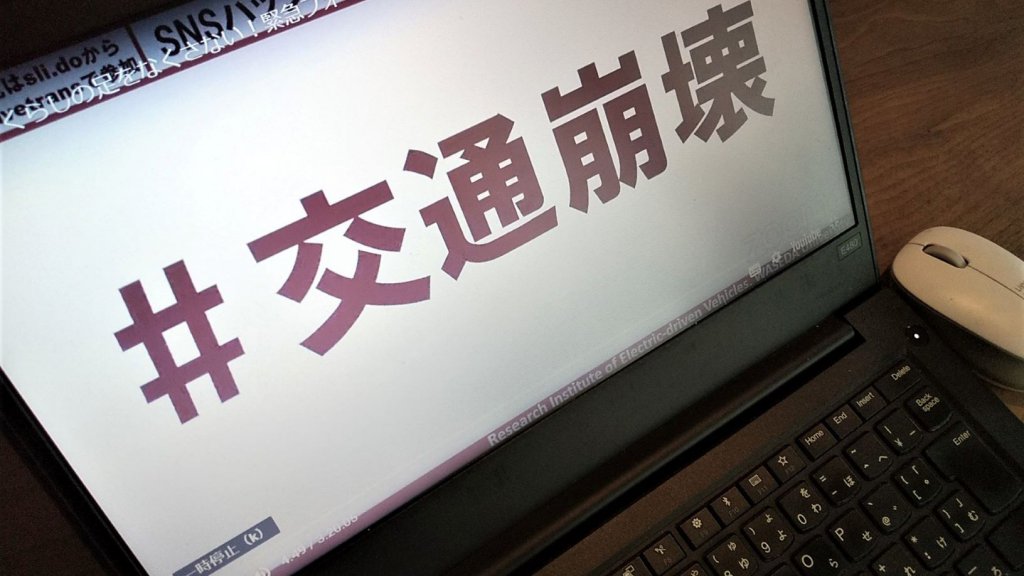新型コロナウイルスによる外出自粛で、多くの業界が打撃を受けた。バスを含む交通業界もそのひとつだ。しかも、乗客が急減しても「走り続けないといけない」使命も負っている。当然、走れば走るほど赤字は膨らむ。
そもそも、地方の路線バス事業は赤字基調で、それに「コロナ」が輪をかけた。まさに「交通崩壊」の一歩寸前。
そこで、交通事業者や大学の研究者、コンサルタントら有志による団体が立ち上がった。オンラインで緊急フォーラムを開催し、業界の現状や今後必要となる取り組みを議論し、支援を訴えたのだ。バスやタクシー事業者、自動車メーカーら800人以上が参加した大型フォーラムの内容を紹介する。
文/写真:バスマガジン編集部
国土交通大臣がバス業界の現場を評価
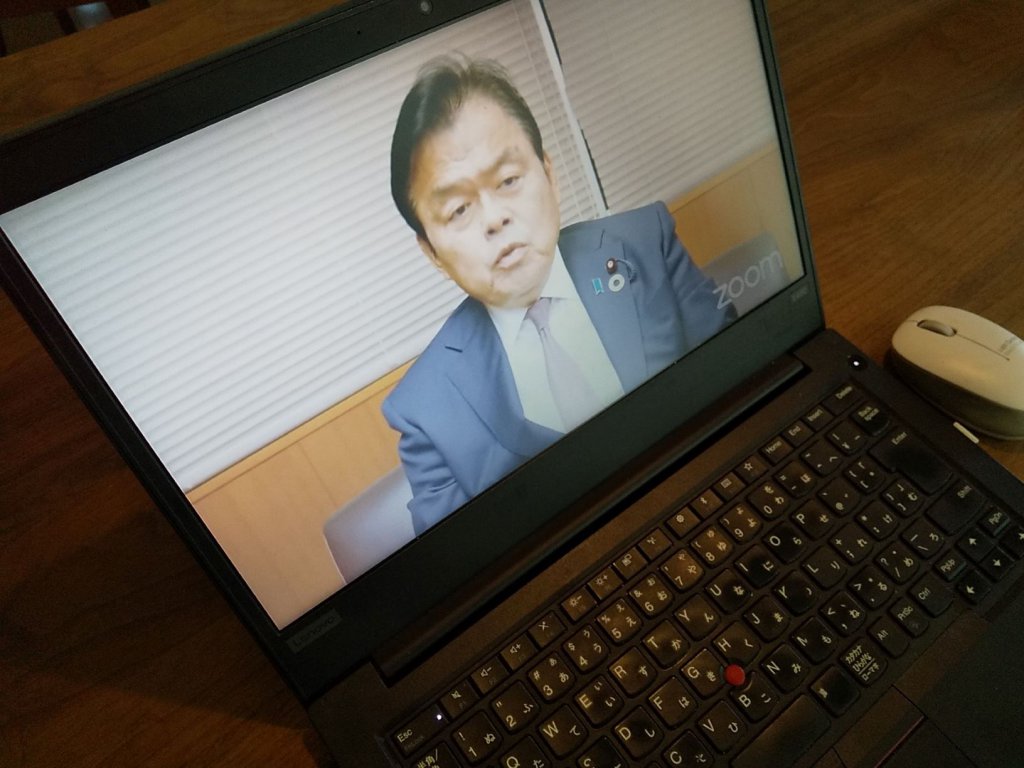
去る5月29日、「続・くらしの足をなくさない! 緊急フォーラム~新型コロナによる交通崩壊をみんなで乗り越えよう!」が開催された。時節柄、登壇者は自宅などからウェブ会議システム「Zoom」上で発言し、その様子を「YouTube」で動画配信する形態。バス業界にもそういう時代が到来したのか、と変化を実感する。
このフォーラムは、4月24日に続いて2度目の開催となった。前回は「緊急事態宣言」まっただ中で、乗客減少により各事業者の経営がピンチだという訴えが相次いだ。
その内容はNHKなどでも報じられたほか、5月19日、参議院での質疑でも採り上げられ、社会の注目を集めた。その後、国土交通省も、業界への緊急支援策を打ち出している。
「緊急事態宣言」解除のタイミングで開催されたこの第二回。今回は、冒頭からなんと赤羽一嘉・国土交通大臣がビデオで登場。
「先日、バス乗務員らとの情報交換会で、マスク着用をめぐる乗客どうしのトラブルが多いなど現場の大変さを認識した」とし、尊い使命と重い責任のため運行を続ける交通事業者、その従業員に賞賛と感謝を表明した。
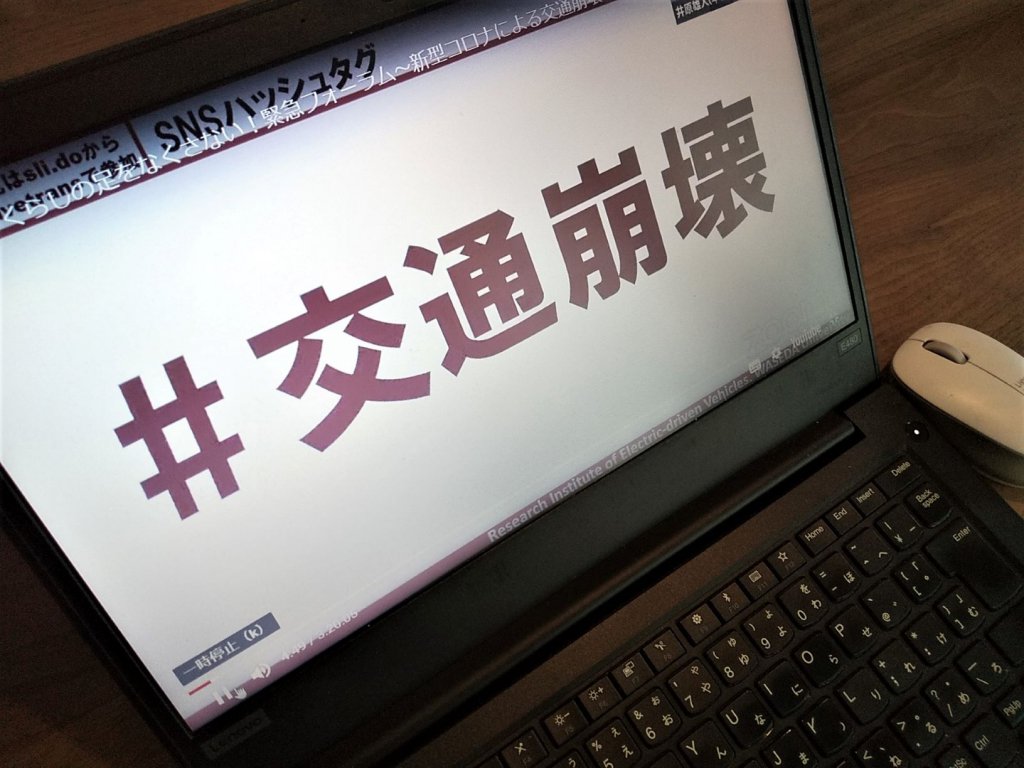
また、138億円もの支援を行うとともに、『アフターコロナの公共交通サービスのあり方』の方向性を打ち出したいとあいさつした。