■元祖・高速車が今も見られるって!?
日本の長距離高速バスの礎を築き上げた東名ハイウェイバス。その路線でごく初期に使われた専用車の「7型」が、2024年現在も残っており、昼間に行けば大体いつでも見られる、との話を耳にした。
今や1960年代に作られた自動車というだけで希少性は抜群、しかも保存車が極めて少ない大型バスとなれば、これは一度くらい見ておく価値アリ……そう思って様子を見に行った。
降り立ったのはTXの終点、茨城県の「つくば駅」。この、つくば駅の近くに7型が展示されているとのこと。駅から土浦方面に県道24号線を1kmくらい歩いて、見えてきたのが「さくら交通公園」。
この公園は乗り物と、子供向けの交通ルール啓蒙をテーマにしている。門をくぐって左側に鎮座している蒸気機関車D51 70号機(なめくじタイプ)を気にしつつ、公園の右奥に目をやると、お目当てのバスがいた。
■東名ハイウェイバスの第1号車!
屋外展示であるが、上屋の下にバスが置かれていて、サビや破損している箇所が少々あれど、全体的にはキレイに保存されている様子。
さくら交通公園の7型は、「747形」というバリエーションで、なんと東名ハイウェイバス第1号車だそうだ。確かに車番747-9901を見ると、下2ケタの「01」が最初に登録された車両であるのをアピールしている。
1969年2月に完成した1台で、シャーシを日野自動車、車体を帝国自動車工業(後の日野車体工業)が製造したとある。シャーシの型式で言うとRA-900P型になる。
この車が東名ハイウェイバス1号車であるのは間違いない。ただし他のメーカーでも、ほぼ同時期に専用設計の国鉄高速車を製造しており、メーカーごとに国鉄の車番は01から割り振られていたため、「第1号車」と呼べる個体は何台か存在する(した)らしい。
公園の展示車両の脇に立ててある解説パネルによると、1969〜1977年6月までの間に137万4021km走ったとのこと。8年で廃車になっているのは、車齢10年以上の高速車が活躍を続ける現在の基準で見ると、かなり短命だった印象を持つ。
もっとも、1年あたりの平均走行距離が17万kmを超えているのも、廃車が早い理由の一つだと思われるが、それまで前例のなかった使い方をする車両だっただけに、走行距離とは別に負荷のかかる箇所が多かったのかも知れない。
つくばで今も簡単に見られる東名ハイウェイバスの747形・第1号車。近くまで寄って眺められるのもあって、日本の長距離高速バス黎明期の面影を探りながら、バスの歴史を想像して楽しむには最高。ロマンあふれる保存車だ。
【画像ギャラリー】つくばで見られる!! 国鉄が生んだ元祖高速車(12枚)画像ギャラリー

















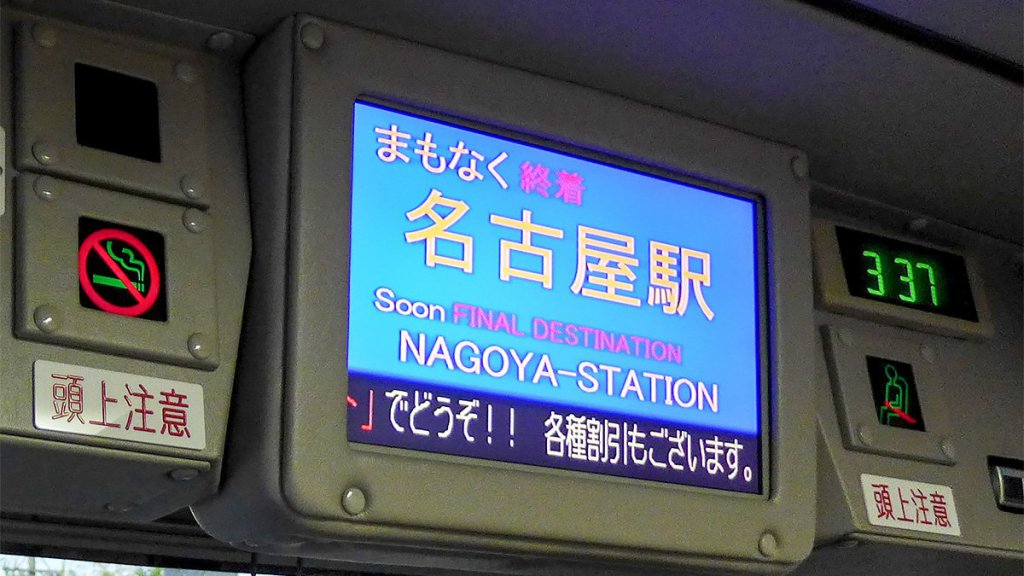
















コメント
コメントの使い方方向指示器も赤色は懐かしいね。
過去には、方向指示器、ブレーキランプ共用のバスもありましたね
マジ!?というほど珍しいものではなく、バスファンの中では有名な場所だと思いますが。
なお、当時の車体が残っていること自体は貴重ではあります。
国鉄バスのユーロビートだな!