関東鉄道は、1965年6月1日、石岡〜鉾田、竜ヶ崎〜佐貫の鉄道線とバス事業を兼営していた鹿島参宮鉄道と、取手〜下館、土浦〜岩瀬の鉄道線とバス事業を兼営していた常総筑波鉄道が合併して誕生した。そのころのバスに会いに行ってみよう。
(記事の内容は、2025年3月現在のものです)
執筆・写真/諸井泉(特記を除く) 取材協力/関東鉄道
※2025年3月発売《バスマガジンvol.128》『あのころのバスに会いに行く』より
■ベッドタウンのインフラとして大正時代からの歴史を持つ
鹿島参宮鉄道は1922年9月3日に設立され、24年6月8日に石岡~常陸小川間で営業を開始した。その後1929年5月16日、石岡~鉾田間が全通した。
また、自動車事業へも進出し、1931年の潮来自動車商会を始めとしてバス路線網を拡大した。さらに竜崎鉄道およびバス会社16社を買収し、茨城南東部及び千葉県北東部までを営業基盤として発展した。
常総鉄道関係では、沿線の重要拠点である水海道町(現:常総市)の合同会社ヤマト自動車商会に、同町から玄関口となる取手までの区間、取手~我孫子間をバスによって押さえられた。
常総鉄道は、対応策としてヤマト自動車商会を買収し、1931年に我孫子町~同町青山、水海道町~取手町、水海道駅前~水海道町~橋本町~淵頭~水海道駅の3路線と貸切自動車の自動車事業直営に踏み切ることとなった。
更に、1934年には真岡・下妻・真壁・筑波・北条・堀込と路線を拡張していた英(はなぶさ)自動車商会や他複数社を買収し、鉄道駅起点の乗合自動車事業を運営した。
鹿島鉄道は関東鉄道から分社し、2007年廃線となった。
しかし、同年4月からは旧鹿島鉄道線に沿って代替バスが運行され、2010年8月からは鹿島鉄道線跡地の石岡駅〜常陸小川駅間7.1キロメートルのうち、石岡〜四箇村駅間の5.1キロメートルを公設民営化方式でバス専用道路として整備し「かしてつバス」(BRT)の運行が開始された。
鹿島鉄道線鉾田駅には関東運輸局の「関東の駅百選」に選定された木造駅舎があった。2007年に廃止されたが、鉄道廃止後も関東鉄道のバスターミナルとして引き続き使用されている。
鉾田駅に隣接して関東鉄道鉾田車庫営業所があるが、停留所名は鉄道が通っていた時代より現在まで「鉾田駅」を名乗っているのは興味深い。
筑波鉄道筑波線は土浦駅と岩瀬駅を結んでいた鉄道路線であった。筑波山麓を巡る路線で岩瀬から都宮への延伸計画もあったが、モータリゼーションの進行などにより乗客が減少、鉾田線(鹿島鉄道)とともに関東鉄道から分離し、様々な合理化を行ったが経営は好転せず、1987年に廃止された。
現在では廃線跡のほぼ全線がサイクリングロードとなっているが、随所に当時のホームあとが残り、当時の名残を留める。
特に主要駅の一つであった筑波駅は、営業当時は筑波山の玄関口としてにぎわった。駅前のバスターミナルは「筑波山口バス停」として引き続き利用されており、旧駅舎も関東鉄道つくば北営業所として当時の面影を留めているのは感慨深いものがあった。
関東鉄道は2025年、鹿島参宮鉄道と常総筑波鉄道が合併して発足60年の記念すべき年になるという。関東鉄道沿線を走るつくばエクスプレスは2025年8月に開業20周年を迎えるが、沿線はベッドタウンとしてめざましい発展を続けている。
関東鉄道も公共交通機関としての役割の重要度を増しており、一緒に働ける仲間も募集中である。
今回、廃線となったこの2つの路線沿線を訪ねてみたが、関東鉄道が長い歴史の中で築きあげられてきた会社であることを改めて伺い知ることができた。廃線になってた今でも鉄道線の残影を感じるのも関東鉄道の魅力である。
【画像ギャラリー】発足60周年なのに100年を超える歴史アリ!? 鹿島参宮鉄道と常総筑波鉄道が合併して誕生した関東鉄道のあゆみ(9枚)画像ギャラリー






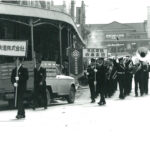























コメント
コメントの使い方