バスで巡るパワースポット、今回は三重県桑名市にある桑名宗社である。三重県の北部に位置する桑名市はすぐ北側に木曽三川が伊勢湾へと流れる場所にあり、鈴鹿山脈や養老の山々を控える。東側には濃尾平野が広がる自然豊かな街である。名古屋への通勤通学も便利で交通網も発達している。本稿には8月のバス占いも付録するので、合わせてお楽しみいただきたい。
文/写真:東出真
編集:古川智規(バスマガジン編集部)
(詳細写真は記事末尾の画像ギャラリーからご覧いただくか、写真付き記事はバスマガジンWEBまたはベストカーWEBでご覧ください)
■三重県桑名市
桑名市内には国内屈指の複合リゾート「ナガシマリゾート」があり、中でも遊園地の「ナガシマスパーランド」はジェットコースターの数が日本一など絶叫マシン好きの聖地ともなっている。また旧東海道の42番目の宿場町として栄え、熱田・宮の渡しから船で結ばれていた。
距離が七里あったということから「七里の渡し」と呼ばれている。ここからは伊勢路に入ることから、ここにある大鳥居は「伊勢国一の鳥居」と言われ伊勢神宮と同様に遷宮の度に建て替えられている。
そんな桑名市の都市部にあるのが今回紹介する「桑名宗社」である。すぐ前を旧東海道が走っており、街道の賑わいとともにまずはここへお参りを、という参拝者も多かったのだろう。桑名最古の神社として約1900年の歴史がある。
そしてこの「桑名宗社」という名称は、桑名神社と中臣神社の両社を合わせたもので、古来桑名の総鎮守として桑名首(くわなのおびと)の祖神を祀ることから桑名宗社という。
■歴史が古すぎて宝物もすごい!
桑名神社は平安時代、延喜式神名帳にその名がある古社で、御祭神は天照大御神の第三御子天津彦根命(あまつひこねのみこと)と、その大神の御子天久々斯比乃命(あめのくぐしびのみこと)の二柱である。
中臣神社の御祭神は天日別命(あめのひわけのみこと)である。天日別命は神武天皇の御代の功臣で伊勢国造の遠祖とされる。元は鹿島神宮の武甕槌大神が春日大社に神幸した際の旧蹟に創祀され、後に桑名神社に合祀されたという。
その後永仁四年(1296年)に奈良の春日大社から春日四柱神を勧請合祀したところから、地域からは「春日さん」と呼ばれ親しまれている。また厄除けの神様と言われている。
伊勢国最初の神社とされ、御祭神との関係から伊勢神宮との関わりが深い神社とされる。また社宝として名刀「村正」の太刀や徳川家康坐像、松尾芭蕉の短冊などを所蔵している。
■2社が1社に収まる珍しい社殿
8月には国指定重要無形民俗文化財・ユネスコ無形文化遺産に指定される「石取祭」が行われる。この祭りは桑名神社の大祭の神事が独立したもので、江戸時代初期から始まったものと言われている。桑名市南郊の町屋川へ行き、清流に禊して採った清浄な栗石を桑名宗社に奉納し祭地を清める行事が祭礼化したものであり、毎年8月第1日曜日(本楽)、前日の土曜日(試楽)に執り行われる。
試楽日は午前0時に神前神楽太鼓を合図に各町内の祭車が一斉に鉦・太鼓を叩き出す。本楽日は午前2時の叩き出しを経て、夕刻からは祭の最高潮となる春日神社(桑名宗社)への渡祭が始まる。鉦や太鼓を叩き出す様子から、天下の奇祭「日本一やかましい祭」と呼ばれ期間中多くの観光客で賑わう。
社殿は桑名神社と中臣神社の両社が入る形になっており、1つの建物に2つの神社という珍しいものだ。拝殿はそれぞれの本殿に対応する形で左右に分かれており、向拝、鈴、賽銭箱等も一組ずつ設けられている。ちなみに正面に見て右側が桑名神社、左が中臣神社である。
境内は広さはもちろん、まずは社殿に向かう左右に綺麗に飾られた提灯が目を引く。地元企業の名前なども多く桑名の人々に深く親しまれているのを感じる。歴史を感じる造りには見えるが、昭和20年(1945年)の空襲により全て焼失している。
戦後昭和29年(1954年)に拝殿が、昭和59年(1984年)には本殿・幣殿、平成7年(1995年)には楼門がそれぞれ再興された。







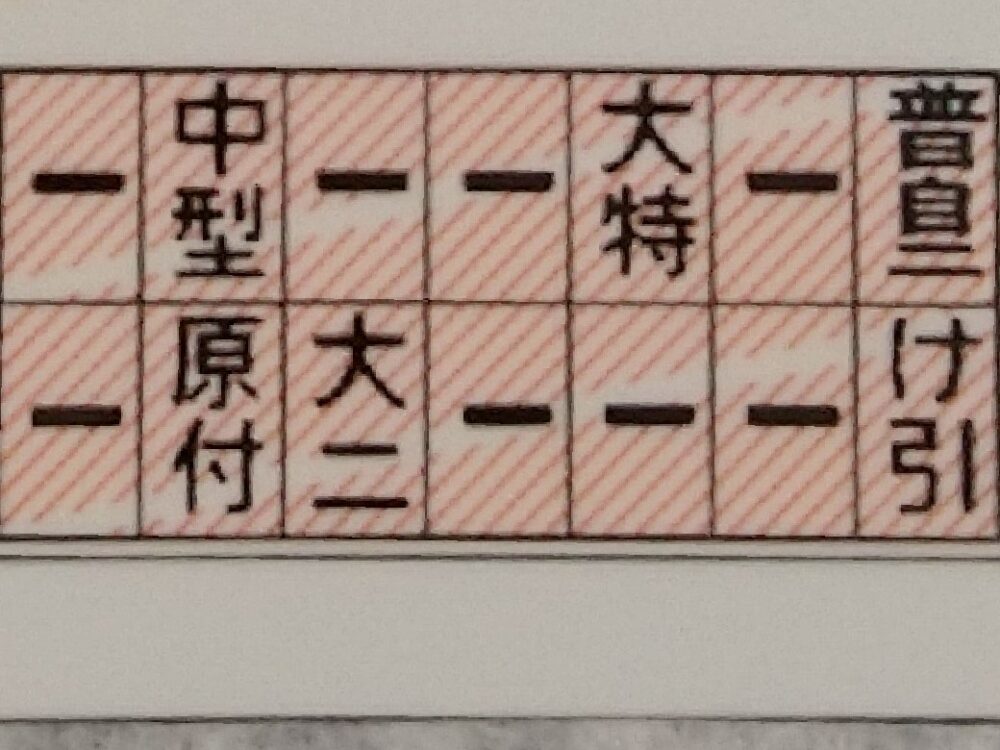
















コメント
コメントの使い方