新幹線には「新○○」と称する駅が各地に置かれている。そんな「新」のつく新幹線駅には大抵、駅名の元になった「○○」の部分に相当する名称の駅が個別に存在するものだ。
文・写真:中山修一
(新のつく駅とそのアクセス手段にまつわる写真付きフルサイズ版はバスマガジンWebもしくはベストカーWebをご覧ください)
■「新」のつく新幹線駅ができるワケ
「新青森」、「新横浜」、「新八代」などなど、フル規格の新幹線に関する限りは、上越新幹線を除いて(あの終点の駅はナシよ)、ほとんどの路線に新のつく駅がある。
新幹線の駅名には、その地域の中でも、全国的に通りの良い地名が選ばれることが多い。ところが、「通りの良い地名」の付いた在来線の駅が既に存在していて、新幹線の駅が在来線と数キロ離れた位置に作られた場合、同じ駅名を名乗るわけにはいかなくなる。
駅名は既得権が最優先であり、在来線の駅名を、後からできた新幹線駅が奪うことはまずない。とはいえ新幹線駅に有名どころの地名は使いたいし、在来線の駅と区別を付ける必要もある。
そんなとき、頭に「新」を持ってきて、その地域を代表するエリアへの、新幹線としての玄関口であることを示すわけだ。
このほか、日本で高速鉄道の建設構想が持ち上がった、ごく初期の段階から計画が存在していた新幹線駅の場合、そのエリアの新しい中心地になることを願って「新」を添えた、とする説もある。
■よく似た名前のアカの他人?
さてその「新○○駅」と、オリジナルの「○○駅」。ちょっと人間関係に例えて、双方の親密さを考察してみたら、どんな感じだろう。
熱々のスープを持っていくにも保温が必須な距離感ゆえに、元々それほど深い縁があったとは言えなさそうで、似た名前の人が隣町にいるのは知ってますけど……くらいのシレッとした間柄に思えてくる。
各地にある新幹線の「新○○駅」と、オリジナルの「○○駅」を訪れてみると、どこも駅周辺の雰囲気からしてそれぞれ全然違うので、共通項はあくまで名前だけで、お互い他人行儀な印象を抱く場所が多い。
そのせいか、「新○○駅」←→「○○駅」間を移動しようと思った際、同じ地名を使っているのだから、双方の距離を感じさせない、ノンストップ直行型のシャトル便が余るほど用意されていて、いつでも好きな時に互いの駅同士をすぐ行き来できる!! といったイメージもそれほど沸かない。
むしろ、新のつく新幹線駅を通るJR在来線や私鉄の電車に関しては一般的な駅と同等、あるいはそれ未満の利便性。殊に電車やタクシー以外の公共交通となれば、都会でもローカルでも“極細”な気がする。果たして実際のところ、どうなっているだろうか。
■新神戸駅と神戸駅のプロファイル
先日ふと、新幹線の「新○○駅」とオリジナルの「○○駅」間における、公共アクセス手段の充実度を、現地へ様子を見に行って写真を撮りつつ確認してみようと考えた。
第1回目に選んだ組み合わせは、山陽新幹線の新神戸駅と、東海道本線/山陽本線(JR神戸線)の神戸駅。直線距離で3.4km、実距離で4kmほど離れた位置関係にある。
神戸駅は1874年5月に官設鉄道の駅として開業。日本では、新橋〜横浜間の次に古い歴史を持つ鉄道線の駅だ。
一方の新神戸駅は新幹線が1972年3月、神戸市営地下鉄は1985年6月に開業。「新神戸」という駅名自体は、山陽新幹線建設より昔の戦前まで遡る。
昭和10年代に、東京〜下関間を最高時速200キロ、所要時間9時間50分で結ぶ「弾丸列車計画」が本格化した際、兵庫県内に専用駅を作ることになり、そこが「新神戸駅」と命名される予定になっていた。
駅の建設予定地は六甲トンネルの出口付近(当時)と、現在の新神戸駅が建っている位置にかなり近かった模様。駅名も立地も、戦争により立ち消えとなった弾丸列車計画の時点で既に決まっていた、とも取れる。
現・新神戸駅は、トンネルとトンネルの間の、狭いスペースに埋め込むような形で作られ、新幹線用としては極めてコンパクトにまとまった駅だ。地形の都合により待避線がないものの、同駅を通る新幹線のうち、全ての営業列車が停まる。

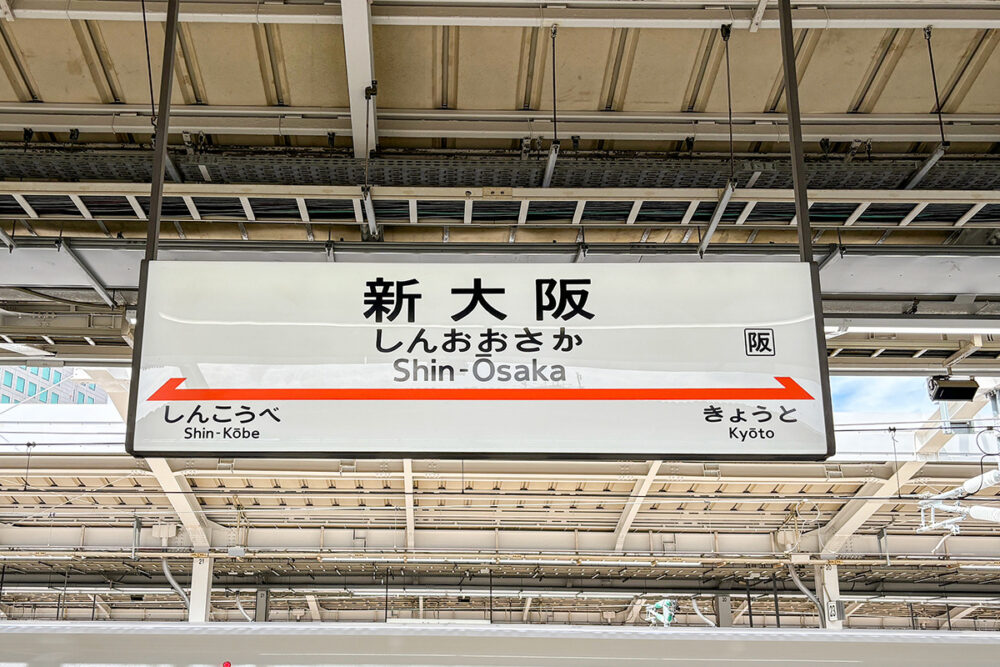
























コメント
コメントの使い方私鉄同士だが茨城県鉾田市は最初は鹿島鉄道だけで鉾田駅があって約1km離れた場所に鹿島臨海鉄道が開通して新鉾田駅になりました。2007年に鹿島鉄道は廃線になり新鉾田駅を「鉾田駅」と言うときが多いです。